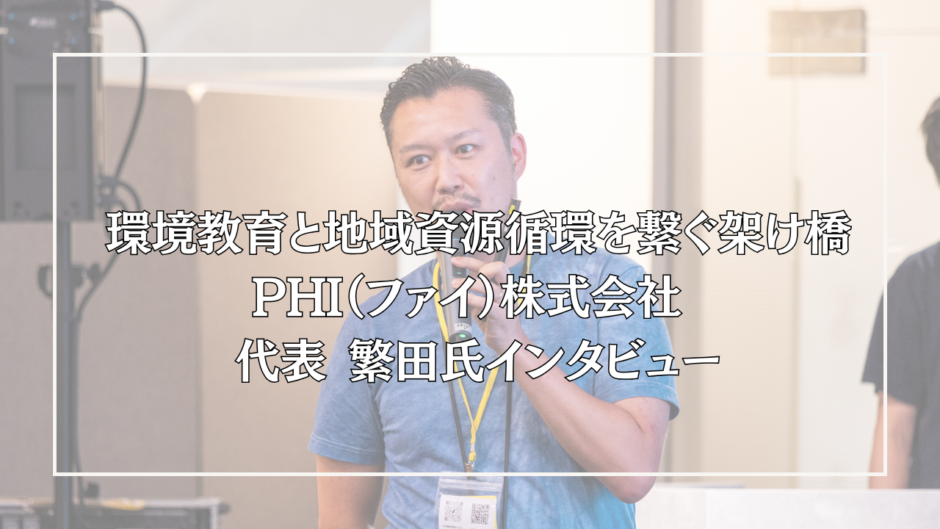環境教育の課題を解決し、持続可能な社会の担い手を育てる―。
環境教育と地域資源循環を繋ぐ架け橋として、革新的な取り組みを進めるPHI(ファイ)株式会社。
代表の繁田氏は、ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社(以下ユニリーバ)に所属しながらSDGsプラットフォーム「UMILE(ユーマイル)」を立ち上げ、115万人を超える登録者を集めるなど、企業内起業家としても知られる人物だ。
2024年に創業したPHIは、広島県の伝統工芸品「熊野筆」と、教育現場で大量廃棄されているプラスチック鉢を融合させることで、持続可能な製品「KACHIIRO」を開発。廃棄資源の新たな活用法を提示するとともに、途絶えつつある伝統工芸品の再生にも取り組んでいる。
繁田氏が掲げるのは「共創」。多様な事業者とのスクラムを組んだ挑戦を続け、本業、副業、社内起業を融合させた独自の働き方で、持続可能な未来を築くその取り組みと情熱を聞いた。

PHI(ファイ)株式会社代表 繁田知延
新卒で商社に就職後、ユニリーバに転職。
ユニリーバ在籍中に社内起業し、SDGsプラットフォーム「UMILE(ユーマイル)」を立ち上げ登録者115万人を超えるプラットフォームに成長させた。
2024年4月、Circular Startup Tokyoに採択されたことを機に、PHI(ファイ)株式会社を設立。
「持続可能な未来の創り手を育む」ことを自身のパーパスとし、環境教育や地域資源循環に関する社会課題解決を推進。
現在もユニリーバに所属し、本業として営業本部、社内起業でUMILE、さらに環境教育観点でPHIの「三刀流」で、地域資源を活用した持続可能な社会の実現を目指し、子供たちが未来を担う力を育むことに情熱を注いでいる。
伝統工芸品と廃材を組み合わせた革新的な取り組み
「熊野筆の生産量はここ数十年程でおよそ70%減少し、職人も減少している。このままでは伝統が途絶えてしまう。何とかしなければという思いがあった」そう語るのは、PHI代表の繁田氏。
2024年5月に創業したPHI株式会社は、環境教育と地域資源循環を軸に、ユニークな事業を展開している。
直近では、広島県の伝統的工芸品「熊野筆」と、小学校の授業で排出される使用済植物用プラスチック鉢を組み合わせた商品開発に着手。開発されたのは、徳島の天然藍を加え、JAPAN BLUEを表現した熊野筆「KACHIRO」。
化粧筆についてはインバウンド需要や大阪万博での展開を予定している。また、同技術を応用し書筆も開発。
こちらは誰もが手に取れる価格で、学校や地域コミュニティで活用されはじめている。
背景には、プラスチック鉢の廃棄問題があった。授業で使用されるプラスチック鉢は、全国で年間300トンもの量がバージンプラスチックで製造され、お役目を終えた後は主にご家庭で廃棄。プラスチック資源の有効活用が出来ていない状況だ。
これら2つの課題を掛け合わせることで、環境教育に繋がるのではないか、と繁田氏は考えた。これは廃棄されるはずの資源を新たな価値に転換するだけでなく、伝統工芸品の継承・発展にも貢献する画期的な取り組みである。

PHI株式会社製品:https://phiselection.base.shop/
共創へのこだわりと組織形成
「共創」という言葉は、PHIだけでなく、多くの企業や団体において重要なキーワードである。
しかし、「共創」を具体的に推進することは容易ではない。事業モデルや組織ルール、価値観が異なる事業者と同じ視座に立つことは決して簡単なことではないからだ。
「“共創”を実現するためには、地方自治体やリサイクル会社、アップサイクル品製造業者、同業他社など、多くの人々に声をかけ、理念や取り組みに共感できる企業や団体と手を組むかを見極める必要がある」と、繁田氏は語る。
その過程では、断られることも多く、途中で破談となることも数多く存在するという。
「効率的でないと思われるかもしれないが、手数を打つことを厭わない。質の良いアウトプットを出すためには多くの人に声をかけ、志に共感し合えた仲間と一緒にスクラムを組み、トライを目指す機会をできるだけたくさん創り出すことが大切」と繁田氏は強調する。
共感を大切にする一方で、スピード感も重視している。SDGs関連の動きは非常に早く、従来のペースではアウトプットが陳腐化してしまうからだ。
そのため、人を信じて資金を投じ、権限移譲を積極的に行い、小規模かつ迅速にスタートさせることの重要性を説く。
具体的には、まず自分が実践しやり方をメンバーに背中で示すことが大切だと述べている。
活動は多岐にわたり、四六時中動いている繁田氏だが、「ビジネスとプライベートの垣根をなくし、ライフワークとして取り組んでいる。与えられた仕事のみで人生の大半の時間を使うのはもったいない。互いの取組に共感し高め合える仲間と楽しみながら、社会的意義とビジネスを両立したアウトプットを継続的に出し続けていくことにフォーカスしている」と語る。
本業と副業のシナジー
繁田氏は、ユニリーバに所属しながら本業と社内起業UMILE、そしてPHIの代表を務める三刀流の働き方をしており、本業で培った海外の知見や技術、そして実績は、PHIの活動に大いに役立っている。
そしてその逆もまた然りである。
「たとえば、ユニリーバでは公立学校へのアプローチが難しいが、個人事業だからこそ切り込める部分がある。また、そこで得た知見は、ユニリーバにも還元できる。」と語る。本業と副業があるからこそ、シナジーが生まれる。
人材や情報の流出を懸念して副業を制限する企業もあるなか、社員の能力と人間性を信頼し、副業にも寛大なユニリーバの「柔軟性」が、それを可能にしているのだろう。
本業への貢献
PHIの活動は、本業であるユニリーバにも大きなメリットをもたらしている。
PHIの環境教育取り組みによって開拓した知見、パートナー、技術等をユニリーバに還元していることも先進性に拍車をかけており、ユニリーバのサステナビリティを体現していることが社内評価され、毎年予算を獲得している。
「会社組織の中で我々の取り組みがどのように見られているかは常に意識している。前例がなく理解が難しい場合もあるため、省庁・自治体の公募事業に積極的にトライし採択を得ること、外部から評価を受けることで、取組内容の正当性を示している。我々の活動が自治体や国に認められたものであることを示すことは、社内でサステナビリティを推進する上で大切なプロセス」と繁田氏は語る。
多くの企業では、サステナビリティ部門が存在するものの、組織の壁や稟議プロセスにより、多くの承認が必要で時間がかかることが多い。また、外部認証等の書類手続きに追われ、本来取り組むべき活動に十分な時間を割けないケースも見受けられる。一方、ユニリーバでは、有志メンバーによる活動が推進されており、柔軟性に富んでいる。
このような体制により、迅速な意思決定と行動が可能となり、サステナビリティの取り組みが効果的に進行している。
サステナブルな取り組みの本質は、一人の困りごとを皆のアセットを活用して解決する姿勢にある。このようなアプローチを実現するためには、組織設計や体制の見直しを検討することは有益かもしれない。
今後の展望
PHI株式会社は、2027年に公立学校への環境教育プログラム導入、また、2028年の海外展開をも視野に入れている。
「スモールスタートでもスピーディーにアウトプットを出すことが大切。そうすることで、周りの目が変わり、人もついてくる。」繁田氏の言葉には、情熱と信念が込められている。環境教育と地域資源循環を繋ぐ架け橋として、PHIの今後の活躍が期待される。
(聞き手:The Lodges.事務局)
プレスリリース配信サービス「SDGs PR Lodge」のご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。
新規会員登録と料金プランをあわせてご確認ください。